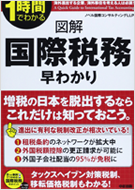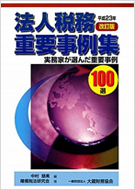最新「OECD移転価格ガイドライン」(2017年版)の注目すべき点(1)
2018年7月、国税庁ホームページにアップされた最新ガイドラインは、2017年7月、OECD(経済開発機構)理事会において改訂承認されものです(以下では、「新ガイドライン」と呼びます)。
これまで全章を日本語で読むことができたのは2010版のガイドラインですから、実に8年振りになります。
さて、ガイドラインの改正された内容については、2012年から始まったBEPSプロジェクト及び同最終報告書から、移転価格の専門家の間では、もっぱら無形資産の変更点などに関心が寄せられてきた向きがあります。具体的には、第6章の「無形資産に対する特別の配慮」についてです。
たしかに無形資産については大幅な改正があり、例年、暮れごろに決まる税制改正大綱で、今年はそれらの内容が少なからず反映されることになるでしょう(平成28年度の税制改正において、移転価格文書化制度が導入されたように)。
ただ、あらためて新ガイドラインを読んでみると、他にも多くの追加や改正が行われたことに気づき、驚きます。
そこでこれから数回にわたり、主だった変更点にフォーカスを当て、若干の解説を試みたいと思います。それでは、まず第1章から始めましょう。
「移転価格分析」の詳細な記述
第1章を読みはじめて最初に目を引くのは、「移転価格分析」という言葉です。これまで無かった用語です。
新ガイドラインは、移転価格分析を2つの段階に分けて説明しています。
第1段階は、「関連者間取引の正確な描写のためのプロセス」と位置付けています。これを聞いただけでは、おそらくすぐには実感できないでしょう。ただ、ここでやろうとすることは、端的にいえば、関連者と国外関連取引とをよく分析してみようということです。国外関連取引を行う日本の法人は何者で、また海外の関連者は何者で、その当事者がいったいどんな取引をしているのかを、十分に洗ってみようというわけです。
第2段階は、国外関連取引にとっての比較対象取引を見つけ出すプロセスです。これまでのガイドラインの第3章で詳述されていた「比較可能性分析」と考えてよいでしょう。
経済的な特徴・比較可能性の要素
では、第1段階の「関連者間取引の正確な描写のためのプロセス」では、いったいどんなことをするのでしょうか。あるいは、どんな視点・着眼点で分析を進めていけばよいのでしょうか。
その際に求められる着眼点が、「経済的な特徴」と「比較可能性の要素」です。
まず、経済的な特徴とは、取引条件、取引が行われた経済的な状況から成ると新ガイドラインでは説明されています。ここで注目したいのが、分析にあたっては「取引条件」からスタートするということです。このアプローチは、新ガイドラインの一貫した考え方といってよいでしょう。
闇雲に分析をはかるのではなく、関連者間で取り交わされた取引条件、つまり契約内容が、はたして第三者が取り得る条件なのかという思考で分析を展開するのです。独立企業間で同じ取引が生じたならば、独立企業がその取引の条件を評価する際に考慮するであろう範囲を特定するために、単に感覚や土台のない分析や議論とならぬように、契約をベースに据えた「取引条件」を切り刻んで分析してみようというわけです。
一方、比較可能性の要素については、2010年版ガイドラインから変更はなく、例の5つです。つまり、①取引の契約条件、②機能分析、③資産または役務の特徴、④経済状況、⑤事業戦略です。
ただし、ここで大いに注目したいのが、②の機能分析において、リスク分析が特出しされていることです。
リスクについては、2010年に、第9章の「事業再編に係る移転価格の側面」が、いわば唐突的に出現し、その中で散りばめて書かれていました。第9章は、実務で発生する事例をモチーフに書かれているため、ガイドライン全体のトーンとしては異質であり、そこで書かれたリスクに対するアプローチなどについて、いったいどのように考えるべきかが不明であったかも知れません。
しかし今回、新ガイドラインでは、国外関連取引全体を貫く根本原理である独立企業原則そのものを扱う第1章に書き込まれたことで、いかにリスク分析が大切かがわかりますし、それ無しには、移転価格分析を行ったとは言えないということになるのでしょう。
リスク分析プロセスの6つのステップ
これまで実務で「機能・リスク分析」といっても、リスク分析はどこか漠然としたものではなかったでしょうか。在庫リスクを負うか、貸倒リスクはあるか、製品保証リスクはどちらが負うか、為替リスクはどちらにあるのか――そうした項目の「ある・なし」で終わっていた感があります。
しかし今回、新ガイドラインは、6つのステップによる分析を具体的に求めています。①経済的に重要なリスクを具体的に特定、②契約上のリスクの引受けの把握、③リスクに関する機能分析、④ステップ①~③の解釈、⑤リスク配分、⑥リスク配分の結果を考慮した取引の価格設定です。
これらの分析でも、契約の分析から実質的にはスタートしていくことになるわけです。
当局が否認できる「2つの特別な状況」の削除
さて、2010年版のガイドラインには、税務当局は、2つのケースにおいて、国外関連者が採用した取引や仕組みを否認することができると記されていました。いわゆる取引の再構築が、税務当局に許されるとしていたのです。具体的には、「D.2 実際に行われた取引の認識」のパラ1.64及び1.65です(ちなみに、同パラは、1995年版(日本語の平成10年9月版)から同じくありました)。
否認できる1つは、「取引の経済的実質がその取引の形式と異なる場合」であり、いま1つが、「取引に関連した取極めが、総合的に判断して、商業的合理性のある形で行動する独立企業が行ったであろう取極めとは異なり、かつ、実際の仕組が税務当局による適切な移転価格の決定を実務上妨げる場合」でした。
さて、この2つのパラが無くなったことで、取引自体の否認や、いわゆる取引の再構築を行うことが、税務当局はできなくなったと早計に考えるべきではないと思われます。
なぜなら、これまで述べてきたように、移転価格分析を2つの段階で捉え、取引条件(契約)からスタートして、より関連者間取引の正確な描写のためのプロセスを強化することで、従前のパラを残すことなく、むしろ不適当な取引は、当然に排除されると見るべきだからです。
けだし、こうした対応がはかられたのは、包括否認の法理や一般否認規定の法制化などについては、各国により立ち位置が異なるため、あえて明記することを避け、新ガイドラインの他のところから、これまでと同様な帰結を導き出せるため、変更したとしても何ら執行に支障がないとの判断があったのではないのでしょうか。
これらの意味からも、新ガイドラインで書かれた「移転価格分析」や「リスク分析プロセス」は、重要視しなければならないものと考えられます。
(続く)