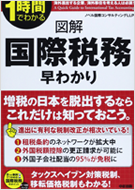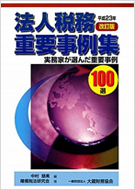最新「OECD移転価格ガイドライン」(2017年版)の注目すべき点(2)
現在、国税庁ホームページにアップされている最新ガイドラインは、2017年7月、OECD(経済協力開発機構)理事会において改訂承認されものです(以下では、「新ガイドライン」と呼びます)。
新ガイドラインは、BEPSプロジェクトの成果物、すなわち、2015年10月のBEPS最終報告書の内容が反映されています。2017年7月から、すでに1年3ヵ月ほど経ちますが、最終報告書から起算すれば、実に3年が経過しています。
新ガイドラインに反映されていない内容
新ガイドラインが採択され公表された以降、今日に至るまで、OECD内で移転価格に関連した動きがなかったのでしょうか。そんなことはありません。大きく2つの事項が実を結んでいます。
1つは、金融取引に関する取扱いです。金融取引については、新ガイドラインの脚注に、「金融取引(資金が、特に無形資産の開発への投資といったプロジェクト・ファイナンスに使用される場合を含む)に関する独立企業間の条件を決定するため、経済的な特性についての追加指針が示される予定。この作業は、2016年と2017年に実施される」とあります。それが実行されたのです。
いま1つが、取引単位利益分割法(利益分割法と同義であり、以下では、「利益分割法」と表記します)についてです。これについても、新ガイドラインの本文において、「現在、第6作業部会では利益分割法の適用について検討されており、本節及び第2章別添Ⅱ・Ⅲの指針は、そこでの結論を受けて改訂予定である。この検討は、BEPS行動計画10に基づくものであり、グローバル・バリューチェーンの文脈において利益分割法、特に取引単位利益分割法の適用を明確化することを目的としている」とあります。
実は、その成果物が、本年6月に仕上がっています。これを見ると、少なからず驚くことがありますが、今のところOECDのホームページで英語で読むしかできません(ただし、月刊誌『租税研究』2018年9月号において、国税庁相互協議室長だった小森敦氏が、「ポストBEPSにおけるOECD移転価格ガイドライン関連作業の進展について」と題した講演録が掲載されており、そこで大変有意義な解説をされていますので、ご興味のある方は、そちらをぜひご一読ください)。
なお、現時点で、第4章(移転価格に関する紛争の回避及び解決のための税務執行上のアプローチ)と第7章(グループ内役務提供に対する特別の配意)について、今後、議論していくであろう諸課題の頭出し(スコーピオン)ペーパーが発表され、本年6月を期限にパブリックコメントが募られてもいました。
このように、実に見逃し難い検討の動きがあります。これらについては、別途、こちらで発信して参りたいと考えています。
無形資産の定義と新ガイドライン第1章
さて、再三ご紹介しているように、BEPSプロジェクトの移転価格における最大のテーマは、無形資産でした。ですから、ついついそれを扱う第6章に目が行きがちですが、実は、第1章にも無形資産に絡んだことが落とし込まれています。そしてまた、第6章の内容を先取りすれば、無形資産の認識や機能リスク分析においては、第1章で示されるアプローチ(前回の本稿で紹介済み)が色濃く反映されています。
では、そもそも新ガイドラインでは、どのように無形資産の定義をおこなっているでしょうか。新ガイドラインは、「『無形資産』という用語は、有形資産や金融資産ではなく、商業活動で使用するに当たり所有又は支配することができ、比較可能な状況での 非関連者間取引においては、その使用又は移転によって対価が生じるものを指すことを意図している」として、実質的には、定義づけることをやめて(断念して)います。これは、これからますます拡大するであろう無形資産を、無理に分類し定義するのではなく、より税務当局が投網を掛けやすいよう、いわば「ぼわっ」と記載してみたということが推測できます。このことは、あえて「マーケティング上の無形資産」(commercial intangible)を定義づけなかったことからもうかがい知れるでしょう。
その一方で、無形資産と扱わないとしたものがいくつかありました。そして、それらが、まさに第1章の中に落ちています。今回はその1つ、ロケーション・セービング扱います。
ロケーション・セービングと移転価格分析
ロケーション・セービングについては、多国籍企業グループが業務の一部を、当初の業務遂行地よりもコスト(人件費、不動産コスト等)の安価な場所に移管する場合に生じるもの、と定義づけています(パラグラフ9.126。以下、表記の仕方同じ)。これに対する移転価格上の分析アプローチについては、ロケーション・セービングの稼得を目的とした事業戦略(事業再編のビジネスを含む)の分析(第 1 章 D.1.5 の議論)を念頭に進めるよういっています(9.126)。
そして、機能分析により、顧客又はサプライヤーに配分されないロケーション・セービングの存在が明らかになった場合で、現地市場における比較可能な企業や取引が把握可能な場合は、現地市場の当該比較対象は、配分されずに残ったロケーション・セービングが複数の関連者間でどのように配分されるべきかに関して、最も信頼し得る指標となる、と指摘し、あくまでも比較法を用いると整理しています。そして、比較法を用いる場合は、差異調整は必要ないとまでいっています(1.142)。
一方、比較対象取引がない場合は、関連者の果たす機能、引受けるリスク及び使用する資産など関連する事実関係の全ての分析に基づくべきであるといっています(1.143)。
ここで注目すべきは、比較対象取引の有無の2つで分けて考えていることです。
ロケーション・セービングに対するアプローチ
さて、ロケーション・セービングに対する分析アプローチについては、次の手順を示しています(1.141)。
- ロケーション・セービングが存在するか
- ロケーション・セービングの金額の特定
- ロケーション・セービングがどの程度多国籍企業グループのメンバーに配分されるか、どの程度非関連顧客またはサプライヤーへ配分されるか
- ロケーション・セービングが非関連顧客またはサプライヤーに完全に配分されずに残る場合、類似の状況で、事業を行っている非関連者が、この残ったロケーション・セービングをどのように配分するか
こうした分析アプローチにより対象とすべき事項として、租税減免や恩典、人件費、不動産コスト、輸送コスト、セキュリティ費用、研修費用などを新ガイドラインは具体的に例示し、原価管理の増分利益・費用の観点などから把握・検討するよういってもいます。
ロケーション・セービングと日本の裁判事例
ロケーションに関連する日本の移転価格の判例として、ホンダのブラジル事件(東京高裁平成27年5月13日判決)があります。事件は、「租税判例百選(第6版)」に掲載されるなど、移転価格における重要な事件といえます。
事件の概要を記せば、ホンダのブラジルの子会社(マナウス地区に所在)が、現地で二輪車を製造・販売していました。日本の当局は、移転価格算定方法として残余利益分割法を用い、所得移転額を計算し課税し、これを不服とした納税者が訴えた事件です。
争点の1つとなったのは、当局が選定した基本的利益の比較対象取引(企業)が、はたしてブラジル子会社の基本的利益を算定するうえで、比較可能性があるか否かでした。
これに対して裁判所は、当局が選定した比較対象取引(企業)は、マナウス地区になく、また、マナウス税恩典に関して差異調整を行っていないことから、比較可能性がないとして、課税を取り消すと判示しました。
さて、本事件を補足すれば、ホンダの子会社が所在する地区は、租税恩典が与えられる場所であり、いわゆるエコノミック・ゾーンでした。そのため、ホンダのブラジル子会社には、税の減免が与えられ、その結果、ホンダとブラジル子会社の合算利益は税の減免部分を含んでいることから、ブラジル子会社の適正利益の計算上は、残余利益の分割対象となる超過利益部分と、通常の営業活動を行うことで得られる通常の利益(つまりは基本的利益あるいは基礎的利益といわれる部分)とを区別する上では、本来、エコノミック・ゾーンであるマナウス地区から比較対象取引を選定すべきであるが、選定できないのであれば、税の減免の分を差異調整する必要がある、と裁判所は考えたわけです。つまり、マナウス地区の租税恩典を、まさにロケーション・セービングと扱った判示でした。
そこで、新ガイドラインを本事件にあてはめてみましょう。
すでに上で示したように、機能分析により、顧客又はサプライヤーに配分されないロケーション・セービングの存在が明らかになった場合で、現地市場における比較可能な企業や取引がある場合は、比較法を用いることとなります。一方、それができなければ、関連者の果たす機能、引受けるリスク及び使用する資産など関連する事実関係全ての分析に基づくべきだとされます。
判決は、前者の考え方を採用し、比較可能性なし、と結論付けたわけですが、そうであるのなら、差異調整は不要になります。新ガイドラインでは、新たに後者の考え方が示されたため(新ガイドラインで、第1章の「D.6 ロケーション・セービング及びその他現地市場の特徴」は新設されました)、比較法を用いることができない場合は、別の検討が行われる必要があり、判示のような結論に至らぬ余地があることになります。
さて、税恩典から生じる利益を誰が取るか(この場合、親会社たる日本のホンダか、ブラジルの子会社か)は、基本的利益の算定には関係しないと見ることもできます。上の後者の考えを推し進めれば、ブラジルのマナウス税恩典を受けられる場所に、戦略的に投資し、事業を失敗すれば、そのリスクは意思決定を行った親会社が取るわけですから、税恩典部分の利益も、親会社が得て然るべきとの論も十分に成り立つことを、今回の新ガイドラインは示していると見ることもできるわけです(この点については、前回の本稿において、「リスク分析プロセスの6つのステップ」を示し、リスクに対して新ガイドラインが詳細な分析を求めていることも論拠となるかも知れません)。
ちなみに、国側敗訴の事件として、他にアドビ事件(東京高裁平成20年10月30日判決)があります。これについては、BEPSプロジェクトを踏まえた場合、納税者が、いわゆる「バイ=セル」取引から問屋取引に変更したことは、まさにBEPS(税源浸食と利益移転)であり、いま同事件が裁判となった場合には、納税者が敗訴する余地が多分にあるとの実務家からの意見も聞かれます。このように考えると、判決と類似の取引であっても、経済環境やそれに対する見方が変われば、判決も変わる余地があるといえます。
以上の視点に立ち、また、新ガイドラインのロケーション・セービングにかかる考え方を加味した場合には、ホンダ事件と同様な取引を行っている事業者にとっては、ホンダ判決があるからその発想でストレートに対応すればよいとはならず、別の言い方をすれば、予測可能性の点で、納税者にとっては難しい対処が突き付けられたと見ることもできるでしょう。
(続く)