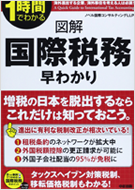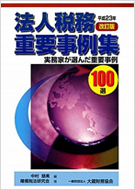最新「OECD移転価格ガイドライン」(2017年版)の注目すべき点(4)~所得相応性基準の創設
11月8日付日経新聞朝刊に、「知財移転への課税強化 財務省、節税行為に対策 将来の利益を勘案」と題した記事が掲載されました。ご覧になられた方もおいででしょう。中身は、無形資産にかかる、いわゆる「所得相応性基準」に関するものでした。記事では、「経済産業省や経済界と協議し、年末にかけて与党の税制調査会で決定する段取りを描く。2019年度の与党税制改正大綱に明記し、来年の通常国会に提出する租税特別措置法改正案に盛り込みたい考えだ。」とありましたから、いよいよわが国でも導入されることでしょう。
今回は、所得相応性基準がテーマです。
BEPS行動計画の中での検討
2015年10月に最終報告が発表されたBEPSプロジェクトにおいて、移転価格の実務家が最大の関心を寄せていたのが、無形資産の取扱いだったでしょう。そのうち無形資産の評価に関しては、どのような方針が打ち出されるのだろうと、とりわけ高い関心が持たれました。
最終報告に先立つ中間報告(2013年7月)では、いわゆるディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)を、移転価格算定方法(手法)の第4の方法とするか否かを、今後議論していく旨も示され、その時すでに所得相応性基準も取り上げられていました。
では、そもそも所得相応性基準とは、いかなるものでしょうか。また、この基準に内在する問題点はないのでしょうか。
所得相応性基準の出現と本質的な問題
国外関連者間で無形資産を譲渡し、譲渡後、その無形資産の価値からして、譲渡時の対価と大きく乖離している事実が判明した場合には、その後、当初の対価との乖離部分を譲渡した法人の収益として認識するという考えかたが、所得相応性基準です。
この考え方を最初に採用したは、米国における1986年のホワイトペーパー(日本における税制改正大綱のようなもの)でした。米国の所得相応性基準は、5年間にわたり毎年、乖離を検証します。乖離幅として20%の基準を設け、20%を超えた場合に、当該金額を検証年度の収益として認識するわけです(一連の検討を定期的調整といいます)。
所得相応性基準には、本質的な問題があると言えるでしょう。
誤解を恐れずにいえば、現代の会計は、取得原価主義と実現主義により成立しています。実現主義においての収益認識は、①財またはサービスの引き渡し、②現金または現金同等物の受領という2つの要件により成立します。①と②とがズレる、例えば、見本品販売、積送品販売、割賦販売などは、会計学では「特殊商品販売」として取り上げ、①と②の要件が完全に一致している一般販売と区別して、収益認識を「いつ」行うのかを、会計学では議論・整理してきたのです。
法人税法基本通達においても、同様の整理が行われ、納税者と当局との間の収益認識に違いが生じないようにしてきました。
こうした取り組みは、近時、国際会計基準(IFRS)を受け、わが国の企業会計基準24号「収益認識に関する会計基準」、いわゆる新収益基準が出され、これにより法人税法第22条の2の新設、法人税法基本通達の改正が行われたことは周知のとおりです。収益認識が、いかに重要なテーマかがおわかりになることでしょう。
そして、このテーマは、まさに会計における一つの研究領域であり、それらにより会計学の一部が形成されてきたという歴史があるといっても過言ではないでしょう。
会計における測定と認識との関係
実現主義により収益を認識する場合、大切なことは、2つのプロセスを同時に行っているということです。つまり、測定と認識です。
認識が、「いつ」収益を実現させるか――「When?」であることは、すでに述べたとおりです。一方、測定は、金額を「いくら」にするかということ――「How much?」です。
今の日本のように物価が安定している時代においては、測定は無意識のうちに行われていますが、短期間で物価が高騰してしまうインフレーション時においては、測定の問題は大変重要な課題でした。わが国でも戦後から1970年代までは、会計学においてはインフレーション会計という一つの学問領域として活発に検討されてきました。世界を見渡せは、アルゼンチンなど物価が高騰している国などでは、今も重要な課題ですし、ブラジルがハイパーインフレに悩まされていたことはさほど古い話ではないのです。
所得相応性基準では、この測定が動くことに他なりません。毎期、当初の対価との見直しを行うことにより、一定の許容される閾値はあるものの、それを超えれば新たに収益認識されるわけですから、実現主義そのものの変更をはかっていることにもなるのです。
後知恵との関係
移転価格にかかる固有の問題としては、「後知恵」の問題があります。
後知恵は、移転価格において実現した結果損益を、取引を行う以前、あるいは、取引当時の状況下であくまでも企業判断の適否を、決して、結果損益が明らかになった時点以降の視点で評価してはならない、という考え方です。
OECD移転価格ガイドラインは、税務当局に対して、後知恵の使用を強くいさめています。例えば、パラグラフ2.136では、「関連者が取引単位利益分割法以外の手法に基づき関連者間取引の条件を決定している場合、税務当局は、その企業の収益実績に基づいて当該条件を評価することになろう。しかし、後知恵を避けるため、関連者が経験したであろう状況と類似の状況の下で、すなわち、関連者が当該取引を開始した時点で知っていた又は合理的に予見し得た情報に基づいて、取引単位利益分割法が確実に適用されるよう留意する必要があろう。パラグラフ 2.12及び 3.74参照。」といっています。2017年版で後知恵は、8箇所記載があるほどです。
しかし、所得相応性基準は、一定の閾値や期間を設けながらも、この後知恵を採用することに他なりません。移転価格の根本的な考え方に立ち返れば、それらに反しているといえ、今後、法令上どのような適用条件が規定されるのかが注目されます。暮れに公表される「税制改正大綱」から目が離せません。
(続く)