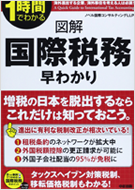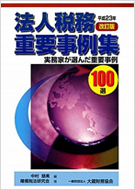平成31年度税制改正大綱公表―移転価格税制の見直しについて(その1) ~更正期間を7年に延長

平成30年12月14日、平成最後となる31年度税制改正大綱が公表されました。今回の大綱は、移転価格税制について見た場合、2015年10月のOECDのBEPS最終報告書を受けた後の平成28年度税制改正に次ぐ、大幅な改正となると言えるでしょう。
改正の主要事項は、次の6点です。
- 更正期間を6年から7年とする
- 移転価格税制の対象となる無形資産の明確化
- 無形資産にかかる、いわゆる所得相応性基準の導入
- 比較対象取引について差異調整の定量化がはかれない場合は、四分位法(インタークォータイル・レンジ)を用いことができる
- 無形資産の独立企業間価格の算定方法として、いわゆるDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)を移転価格算定方法の1つとして用いることができる
- 地方税法について、【1.】から【5.】の改正を反映させる
すでに、【3.】の所得相応性基準については、本サイトの2018年12月4日付「最新『OECD移転価格ガイドライン』(2017年版)の注目すべき点(4)~所得相応性基準の創設」にて取り上げているため、詳細事項についてはそちらをご参照ください。なお、法令化が予定されている大枠の内容は、米国内国歳入法のそれと類似しており、予測便益との乖離が20%超の場合に発動される模様です。
さて、今回を含め数回にわたり、平成31年度税制改正大綱における移転価格税制の見直しについて取り上げたいと思います。初回は、【1.】の更正期間7年に延長です。
28年振りとなる更正期限の延長
更正期間の延長は、平成3年に、従来3年であったものを6年とする改正が行われました。今回、更正期間を6年から7年へとする改正は、平成3年以来のものであり、実に28年振りになります。
そこで、平成3年の改正と対比することで、見えてくるものがあるのではないかと考え、平成3年の改正にともない当局が公表した「改正税法のすべて」を見てみることにしましょう。
平成3年「改正税法のすべて」
「改正税法のすべて」は、今でいうところの「税制改正大綱」に匹敵するものであり、改正内容が詳述されていたものです。さっそく中身を見てみましょう。
「3 更正決定等の期間制限の改正」の「⑴改正の趣旨及び内容」において、次のように解説されています。
「移転価格税制は、端的に言えば、国外関連者との取引が独立企業間価格で行われていない場合には、その取引を独立企業間価格に引き直して課税所得を計算するというものです。企業が法人税の申告に当たってこれに従っていなかった場合には、当然ながら、課税当局は更正処分を行うことになります。当局が更正(無申告の場合は決定)できる期間については国税通則法にその定めがあり、偽りその他不正の行為がある場合には7年、その他の場合には3年(無申告の場合は5年)とされています。この原則的なルールに従うと移転価格事案については、通常、申告から3年経過すると更正処分は行えないことになります。
しかしながら、移転価格事案の調査に当たっては、取引の内容、取引条件等の分析に多大の時間を要するほか、国外の関連会社などからの情報収集も必要となります。本制度の下では、課税当局は、海外の関連会社の有する情報の提供を求めることができることとされており、また、租税条約に基づく課税当局間の情報交換の途も開かれてはいます。しかしながら、課税当局がいかに効率的な調査を実施しようとしても海外の関係企業あるいは租税条約締結国の協力いかんにより調査が長引くことは避けられないという事情があります。また、移転価格税制は、租税条約締結国の一方の国が移転価格課税を行った場合、経済的な二重課税を排除するため、他方の国が取引の相手方である関連企業の納税額を減額調整(これを対応的調整と呼んでいます。)するという租税条約上のスキームが用意されています。例えば、米国の課税当局が日系子会社の親会社からの製品の購入価格が独立企業間価格より高いとして同子会社の課税所得を増額する更正処分を行った場合、わが国は取引の相手方である日本の親会社の課税所得を減額する必要があります。無論、この調整は、自動的に行われるわけではなく、妥当な取引価格について両課税当局間の合意が成立した場合に限られますが、更正処分できる期間が諸外国と比べて短すぎると実質的にみてわが国と諸外国との間で相互主義が保たれないことになるおそれもあります。
諸外国の一般的な更正、すなわち、脱税以外の更正の期間制限についてみてみると、アメリカでは原則3年、申告洩れが申告所得の25%を超えるときは6年となっています。更に、課税当局と納税者との合意により更正できる期間(時効)が延長できるほか、最近の改正で財務長官が納税者に対し特別サモンズを発し、これに関して法廷手続が進行している間は時効の進行が停止することとされています。イギリスでは6年、ドイツ、フランスでは4年、ただし、ドイツでは臨場調査の開始により時効が停止されるようです。カナダでは原則は3年となっていますが移転価格事案に限っては6年に延長されています。
このような移転価格税制における税務調査の困難性と諸外国の制度を考慮し、今回、課税当局が更正決定できる期間について次のような改正が行われました。すなわち、次の更正決定又は賦課決定については、それぞれ次の日又は期限から6年間行うことができることとされています。」(下線は筆者)
上の説明を要約すれば、
- 国外関連者の情報収集の困難性
- それに伴う調査の長期化
- 諸外国との相互主義(レシプロカル)
- 諸外国の移転価格税制との均衡
となるでしょう。それらは、まさに引用文の最後の「移転価格税制における税務調査の困難性と諸外国の制度を考慮」したことにあったと言えるでしょう。
諸外国の更正期限等
それでは、主要諸国の現在の時効の状況を概観してみましょう。
- イギリス:原則、会計年度終了後4年
- ドイツ:原則4年(租税回避や不正の場合10年)
- フランス:原則3年(悪質な租税回避等の場合5年)
- カナダ:原則7年アメリカ:原則3年だが、申告洩れが申告所得の25%を超えるときは6年。無申告、悪質な租税回避の場合は更正期限なし
以上を見る限り、平成3年のわが国の税制改正以降、主要諸国の時効は当時とほぼ変わらないことがわかります。つまり、平成3年の「改正税法のすべて」で理由とした相互主義の考え方に基づく「諸外国の制度を考慮」するようなインセンティブは、今回の税制改正の上では、無かったのではないかと推察されます。
近年の移転価格税制を取り巻く状況
近年の移転価格税制を取り巻く状況は、平成28年度税制改正に基づく移転価格文書化の導入により、顕著な変化があったと言えます。納税者が、みずから国外関連取引に関する事実関係を説明し、移転価格上の問題の有無を検討した文書を、確定申告書の提出期限までに作成・保管することが義務化されたからです。これにより税務当局は、日本の納税者ばかりか、国外関連者の機能・リスクに関する情報を理解することができるようになりました。また、国別報告書やマスターファイルの作成義務のある企業グループにあっては、グループ全体の事業概要、構成する会社の各々の機能や主要財務数値などをも当局は知り得ます。
このことは、平成3年の「改正税法のすべて」で述べていた「移転価格税制における税務調査の困難性」が、各段と解消されたことを意味するでしょう。
そして、今回の更正期限の延長です。ここから垣間見られることはいったい何でしょうか。
課税強化の流れなのか?
1点考慮すべきは、平成25年1月1日から施行された国税通則法(以下、「改正通則法といいます。)です。これにより、納税者の減額更正を求めることができる「更正の請求」の期間が5年に延長されることにあわせて、税務当局がする増額更正の期間制限が、改正以前の3年から5年に延長されました。従来の偽りその他不正の行為がある場合の7年はそのままであったことから、移転価格のみ6年であることが異質な取り扱いだとの懸念があったのかも知れません。
しかしながら、そうであれば、偽りその他不正の行為である場合の7年を、移転価格にストレートに適用するのには疑義が生じます。
つまり、移転価格については、先の移転価格文書化の効果に鑑み、原則5年とし、悪質なケースについては7年という選択もあったのではないか、と思われるからです。
そうではなく、税務当局により有利となる7年という更正期限の1年の延長は、やはり移転価格課税の強化だと言えるのではないでしょうか。
こうした流れは、むろん平成24年(2012年)からスタートしたBEPS行動計画、その成果物である27年(2015年)10月の最終報告書、さらには、現在も取り組みが続いている通称、BEPS防止措置実施条約などの影響を色濃く反映した、税務当局寄りの、今回の更正期限の延長だったと言えるのではないでしょうか。
更正期限の延長が投げかける問題点と望まれる今後の対応
⑴再調査制限規定
納税者にとって今回の改正は、税務調査においてひとたび問題が指摘され、過年度においても同一のプライシングを行っておれば、1年余分に遡及されるわけですから、課税リスクが高まったことになるでしょう。そのため、どうにかして遡及適用を回避したいとのインセンティブが働きます。
こうした視点で見た場合、改正通則法の再調査規定とのかかわりが注目されます。平成31年度税制改正の適用は、平成32年4月開始の事業年度となりますから、それ以降の取扱いとして更正期間7年となるのでしょう。
過去の事業年度においてすでに調査が行われていたような場合には、いかなる場合に当局が再調査可能かの議論が、ますます行われることになるでしょう。
国税通則法上は、その通達5-7において、再調査可能な場合として「新たに得られた情報」について説明していますが、依然として、移転価格のケースでどのような情報であれば新たに得られた情報に該当するのかなどが不明です。そのため、納税者と当局の間で議論されたり、場合によっては、これ自体が争点として訴訟等になることも予測されます。
当局には、ぜひとも具体的な例示の公表をお願いしたいところです。
⑵デミニマス・ルールの導入
わが国の移転価格税制は、一定額を示し、その金額を下回った場合には、移転価格税制の適用はないという規定にはなっていません。また、移転価格文書化についても、作成が必要となる基準額を示すものの、それを下回った場合には義務はないものの(文書化免除取引)、当局が必要と認めた場合には、移転価格文書に匹敵する書類等の提出等が納税者に求められることになります。つまり、国外関連取引があれば、すべての納税者が、移転価格税制の適用を受けるという建付けになっているのです。
しかし、更正期限が7年と長く、また、移転価格上の問題の有無を疎明する移転価格文書の作成には実際にコストがかかることなどから、一定の基準額に満たない国外関連取引には、移転価格税制の発動を行わないとする、いわゆるデミニマス・ルールの導入の検討が望まれます。
デミニマス・ルールは、BEPS行動計画4「利子控除制限ルール」や同12「義務的開示制度」でも導入が議論されているところであり、移転価格分野における特殊な議論でないことから、納税者の負担やモラルハザードなどのコンプライアンス・マターとともに考慮され、わが国にもぜひとも導入が望まれます。
以上の諸点が、【1.】の更正期間7年に延長から考えられる一端です。
(本シリーズつづく)