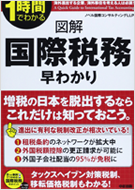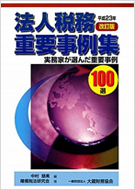平成31年度税制改正大綱公表―移転価格税制の見直しについて(その2) ~四分位法の利用【1】

第2回目は、「比較対象取引について差異調整の定量化がはかれない場合は、四分位法(インタークォータイル・レンジ。以下、「四分位レンジ」といいます。)を用いことができる」とする改正について取り上げます。
今回の改正の意義を、より正確に理解するには、現行の四分位レンジの取扱いについて理解しておくことが有用でしょう。そこで、本テーマについては、2回にわたり解説をいたします。その1では、現行の幅(レンジ)と四分位レンジの扱いについて見ていくとしましょう。
1 四分位レンジとは何か
そもそも、四分位レンジとは何でしょうか?――
これは統計において利用されるものです。一定の数量のデータ(母集団)に対して、特定の値との相関関係を見出す際に、母集団の均一性を確保するうえで、データのばらつきから生じる異常値を排除する方法といえます。具体的には、全データを4つの階層に分け、最上層と最下層を除いた、つまり上下25パーセントを割愛し、内に残る50パーセント部分を対象として分析を行うものです。
しかしこれは、誤解を恐れずにいえば、母集団が、(すみません言葉が汚いのですが)「糞みそ」であることから、より均一となるように上下25パーセントの異常値を排除するということにもなりかねません。
本来、いかなるデータ分析も、データ分析を行うに足る十分な数量の母集団が確保されていることが重要であり、四分位法の採用においても、これがスタートラインとなります。この点は、統計的な手法を用いれば精度が増すといった誤解や盲信を抱くのではなく、よく念頭に置いておく必要があるでしょう。
逆に、四分位レンジは、データのばらつきを、あくまでも前提に置き用いられる方法であることも、理解しておくことが必要でしょう。つまり、比較可能性が真にはかられているのであれば、フル・レンジで何ら問題がないことになります。そこに、わが国ではこれまで課税の局面でフル・レンジを採用してきた根拠があり、以下の取扱いとなっているのです。
2 わが国の現行の取扱い
わが国の移転価格税制では、独立企業間価格は1つである、という発想に立っています。これは、移転価格の法令である租税特別措置法第66条の4第1項において、「(前略)当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるとき(後略)」とあることからわかります。
ただ、法令が、複数の比較対象取引があることを否定しているわけでもありません。複数ある場合は、同第2項ニを受け、施行令第39条の12の6号の適用を受ける、とされているのです。つまり、「準ずる方法」として法令の適用が可能だと考えられているのです。そして、実際の計算は、平均値を用いられてきました。
しかし、2010年のOECD移転価格ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)の改訂において、幅(レンジ)を認めるパラグラフ(当時の番号で3.55及び3.60など)が盛り込まれました。つまり、調査を受ける納税者の実績値が、複数の比較対象取引により形成されるレンジ内にある場合は、移転価格上の問題はないと明記されたのです。そして、レンジを形成する一形態として、ガイドライン上、初めて四分位法が登場したのです。
そこで、わが国では、23年度の税制改正大綱において、独立企業間価格の幅(レンジ)の取扱いの明確化をはかることが示され、明確化は、租税特別措置法通達において、次のようにはかられたのです(番号は現行の番号)。
(比較対象取引が複数ある場合の取扱い)
66の4(3)-4 国外関連取引に係る比較対象取引が複数存在し、独立企業間価格が一定の幅を形成している場合において、当該幅の中に当該国外関連取引の対価の額があるときは、当該国外関連取引については措置法第66条の4第1項の規定の適用はないことに留意する。(平23年課法2-13「二」により追加)
さらに、この取り扱いを明確化するために、移転価格事務運営要領(以下「指針」といいます。)の「3-2⑴」(調査に当たり配意する事項)と、「4-5」(比較対象取引が複数ある場合の独立企業間価格の算定)が置かれました。少し長いのですが、各々の規定を見てみましょう。
(調査に当たり配意する事項)
3-2 国外関連取引の検討は、確定申告書及び調査等により収集した書類等を基に行う。 独立企業間価格の算定を行うまでには、個々の取引実態に即した多面的な検討を行うこととし、例えば次の(1)から(3)により、移転価格税制上の問題の有無について検討し、効果的な調査展開を図る。
(1) 法人の国外関連取引に係る事業と同種で、規模、取引段階その他の内容がおおむね類似する複数の非関連者間取引(以下「比較対象取引の候補と考えられる取引」という。)に係る利益率等の範囲内に、国外関連取引に係る利益率等があるかどうかを検討する。
(2) (以下、省略)
(注)下線部分は、筆者による。
(比較対象取引が複数ある場合の独立企業間価格の算定)
4-5 国外関連取引に係る比較対象取引が複数存在し、当該比較対象取引に係る価格又は利益率等(国外関連取引と比較対象取引との差異について調整を行う必要がある場合は、当該調整を行った後のものに限る。以下「比較対象利益率等」という。)が形成する一定の幅の外に当該国外関連取引に係る価格又は利益率等がある場合には、原則として、当該比較対象利益率等の平均値に基づき独立企業間価格を算定する方法を用いるのであるが、中央値など、当該比較対象利益率等の分布状況等に応じた合理的な値が他に認められる場合は、これを用いて独立企業間価格を算定することに留意する。
(注)下線部分は、筆者による。
指針「4-5」のポイントは、あくまでも平均値を「原則」としつつも、「中央値など、当該比較対象利益率等の分布状況等に応じた合理的な値」を認めるという点です。
3 四分位法の利用
ここまで見てきたなかでは、四分位レンジという用語は登場してきません。これが登場するのは、指針の別冊事例集の中においてです。
事例1の解説5において、「事務運営指針 3‐2(1)の検討においては、必要に応じて四分位法によるレンジ等を活用することが適切な場合もあることに留意する。」と述べられているのです。
4 四分位法に対する誤解
日本の移転価格税制上、レンジが出てくる局面は、大きく2つあるといえるでしょう。1つは、移転価格の蓋然性のチェックの局面です。2つ目は、独立企業間取引における適正利益率(あるいは価格)の検証の局面です。
⑴ 移転価格の蓋然性のチェック/テストの局面
「移転価格の蓋然性のチェック/テスト」とは、聞きなれない言葉かも知れません。この用語は、当局や実務家が一般によく用いている俗語です。
移転価格の調査は、概して長期間に及ぶことから、当局の調査官が調査をスタートして一定の時期が来ると、見極めを行います。つまり、調査を本格的に進めるか、それとも調査を終了させるか、を見極めるのです。この見極めをはかるうえで、所得移転の蓋然性の有無が問題となります。
ポイントは、①価格の歪み、②売上高営業利益率などの特定の率が高く/低くないか、③営業利益額の配分が歪んでいないか、④利益剰余金の急激な増減はないか、などです。これらのポイントは、指針の3-1(調査の方針)や3-2(調査に当たり配意する事項)に記載されている事項などでもあります。
実は、この局面で、②の率の検討の際に、四分位レンジが用いられるのが通常です。とりあえずの比較対象取引を選び、そこから導き出されるレンジを、四分位法で形成し、調査を行っている法人の実績値がレンジの枠内にあれば、移転価格の蓋然性がないとされるのが、ここでの一般的なアプローチなのです。
⑵ 独立企業間取引における適正利益率(あるいは価格)の検証の局面
法人が作成するローカルファイルのゴールとなる経済分析、すなわち適正利益率の算定においては、四分位レンジが用いられることが圧倒的に多いでしょう。また、事前確認(APA)において、同様に適正利益率の算定にあたり、四分位レンジが圧倒的に多く用いられています(APA事案の四分位レンジの使用については、事例集27の解説3において認められています)。
実は、この点などから、課税においても、当然に、四分位レンジが用いられるのだと誤解している人が多くいるのです。
しかし、課税においては、これまで見てきたように、まず比較対象取引は1つという発想からスタートしているため、比較対象取引が複数ある場合には、その平均値を用いるものと考えられてきたのです。
このことは、課税の局面では、比較可能性がきわめて高い比較対象取引が複数あるわけですから、理論的には、形成されるレンジの幅はある一点に限りなく収斂しているであろう、という暗黙的な理解に拠っているといえます。ですから、それらによって形成されるレンジは、おのずと狭いものだという前提があるわけです。
一方、所得移転の蓋然性のチェック/テストの局面においては、調査官による調査期間は短く、比較可能性を確保するに足る精緻な分析は行われていないことから、おのずと粗い比較対象取引の候補を選定することになります。ある意味、比較可能性の低い比較対象取引の候補が混ざっていることを許容しているわけです。そのため、おおざっぱな捉え方であっても、比較可能性の乏しい異常値を上下25%ずつ除外することにより、比較可能性の精度をより上げられる統計的手法の四分位レンジを用いるというわけです。
では、どうしてAPAにおいて、この統計的手法である四分位レンジを用いるのでしょうか。APAでは、比較可能性が乏しい比較対象取引を選定してよいということなのでしょうか。そんな疑問を抱く読者の方もいることでしょう。
APAにおいて四分位レンジの使用が認められるのは、APAが、納税者にとって予見可能性の確保のためのツールであることに起因します。
納税者は、制限された情報をもとに比較対象取引を選定するしかありません。ほとんどの場合が、公開データをもとに選定することになり、当局が課税を行う際に選定するような精度のある比較対象取引は確保できないのです。
例えば、比較対象取引の候補にかかる製品やセグメントなどの情報が十分には得られず、結果として、全社損益による比較対象「取引」ならぬ比較対象「企業」とならざるを得ない場合もあるのです。いや、それが一般的だというのが現状といえるでしょう。そのため、雑多な比較対象取引の候補も含まれてしまうことから、四分位レンジを採用し精度を上げようということになります。
なお、APAにおいても、国によっては四分位レンジを認めていない国もあります。二国間によるバイラテラルAPAにおける四分位レンジの採用は、あくまでも各国の権限ある当局間のオプションにすぎません。
さて、ここまでで明らかになったように、四分位レンジの採用は、移転価格税制上、きわめて限定的に取り扱われており、これまでは、運用も含め、課税における比較対象取引の選定では決して利用されてきませんでした。
しかし、今回の税制改正においては、比較対象取引について差異調整の定量化がはかれない場合に限るものの、四分位レンジを用いことができるわけですから、課税における局面で利用されることになることから、たいへん大きな改正点といえます。
では、どうしてそのような改正が行われるのかについて、2010年のガイドラインの改正点も交えながら、次回、説明を行いたいと思います。
(つづく)