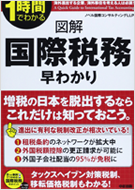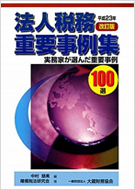平成31年度税制改正大綱公表―移転価格税制の見直しについて(その2) ~四分位法の利用【2】

今回も前回(2019.02.05)に引き続き、「比較対象取引について差異調整の定量化がはかれない場合は、四分位法(インタークォータイル・レンジ。以下、「四分位レンジ」といいます。)を用いることができる」とする改正について取り上げます。
〇改正案
〔差異調整方法の整備〕
比較対象取引の利益率を参照する価格算定方法に係る差異調整について、定量的に把握することが困難な差異があるために必要な調整を加えることができない場合には、いわゆる四分位法に基づく方法により差異調整を行うことができることとする。
前回のコラムの要点を簡記すれば、四分位レンジは、これまで当局が課税する局面では用いられてこなかったということです。
ところが、今回の税制改正では、「比較対象取引について差異調整の定量化がはかれない場合」との条件付きながらも、課税に際しても認められるということは、これまでの運用の大転換といってよいでしょう。
何が大転換かは後述するとして、こうした改正が行われるからには、何らかの背景事情があったと考えるべきでしょう。そうした背景は、今後、当局の担当者が講演や本などを通じて、おそらく解説されるものと考えますが、ここでは筆者なりにそのあたりの背景を模索してみたいと思います。
1 税制改正の背後に事案ありき
一般に、税制改正においては、単に当局サイドが財務省主税局に何らかの改正要望を行えば税制改正が行われる、というものではありません。とりわけ今日のように納税者の権利意識が強くなり、また、改正の結果が納税者にとって何らかの不利益となる改正は、経済界の抵抗も強く、簡単にできないのが実状です。
しかし、例えば、グローバル・スタンダードの観点や各国との約束事、協調関係から求められる事項などは、それ自体が一種のモウメンタムとして働き、一定程度納税者の不利益や経済的負担があろうとも改正されます。その最たる1つとして、OECDによる BEPS行動計画13の移転価格文書化にかかる最終報告書(2015年10月)を受け、平成28年度(2016年)の税制改正により導入された、移転価格文書化が挙げられます。
では、今回の四分位レンジの課税への援用については、そうしたモウメンタムはどこにあったのでしょうか。BEPSでの各国共通事項であったのならすんなりと理解できるのですが、そうした議論がストレートに行われた風でもありません。
ここで考えられるのが、裁判事例です。多くの税制改正がそうであるように、移転価格税制においても裁判の判決が税制改正の誘因となることがあります。
では、はたして近年、該当するような事件があったでしょうか。
2 ホンダ・ブラジル事件
すぐに想起される裁判例として、東京高判平成27年5月13日確定のホンダ・ブラジル事件があります。この事件については、金子宏東大名誉教授の最新の『租税法』(第23版)の注釈で、次のように解説がなされています。長いですがその全文を引用してみます。
「所轄税務署長が、本田技研工業KKがブラジル子会社(アマゾン州のマナウスフリーゾーンに立地)から、二輪自動車の部品等の販売、技術支援等の役務提供の対価として支払を受けた金額が、独立企業間価格にみたないとして、残余利益分割法を用いて独立企業間価格を算定し、移転価格税制を適用した事案について、マナウスフリーゾーンの域外に立地している複数のブラジル法人を比較対象として選定し、それらの法人の平均総費用営業利益率と比較して同子会社の総費用営業利益率が高いのは、本田技術の製品の優秀なことや、同社の技術支援や無体財産権の供与によるものではなく、ブラジル政府によるマナウスフリーゾーンに立地した企業に対する税負担の減免の恩恵によるものであるから、同子会社の総費用営業利益率が高い部分の利益は、残余利益分割法の適用上、基本利益に参入すべきものであって、これを残余利益に参入して独立企業間価格を算定した更正処分は違法であるとした例として、東京地判平成26年8月28日(未公刊)参照。控訴審の東京高判平成27年5月13日(未公判)も同旨の理由で、国の控訴を棄却した。」
この判事は、まず、マナウスフリーゾーンは経済特区であるため、比較対象を選定するのなら同じ税の減免を受けている同経済特区から選定すべきであり、それができない場合は、何らかの差異調整を行うべきであり、それをして比較可能性が保持されることを意味します。
しかし、このことを厳密に行おうとした場合に、第一に、はたして同一の経済特区に比較可能性を有する企業があるのか、という疑問に直面することでしょう。
読者の中には、所属する企業の子会社が海外に進出しているという方もおいででしょう。海外にはいくつも経済特区がありますが、特定の経済特区に所属する企業が50社もあれば大規模な方で、20数社、10数社の特区もざらです。そうした企業の中から、例えば、比較対象企業を選定することは不可能に近いでしょう。
なぜなら、ホンダ・ブラジル事件のように基本的利益部分に総費用営業利益率を用いる場合、わが国の移転価格税制上、同種、または類似の棚卸資産等であることが求められますが、そうした事業を営む企業をその経済特区で見い出すことができないからです。仮にできたとしても、そもそも関連者間取引であり採用できないでしょう。
では、他の経済特区から比較対象取引を選定できるかとなると、これまた問題が生じます。理屈の上では選定した比較対象取引の候補の企業が所在する経済特区の税の減免を、経済特区ごとに当局は把握する必要がでてきます。日本の会社に限らず、海外進出している企業は、そこに「うま味」があるからこそ進出するわけで、その多くは、やはり税を含んだコストが安いからです。逆に言えば、経済特区にしか、海外進出をしないといっても過言ではないでしょう。つまり、いちいち経済特区ごとの税の減免を当局は把握する必要がでてくるのです。
ホンダ・ブラジル事件では、別に考慮すべき要因もあったようです。それはマナウス地区が、「ブラジル中央の市場とは3,000kmからの距離があり、工業製品の搬出には大きなハンディキャップとなる。政府はそれをカバーするための税制恩典を発令し、工業誘致を開始した」(「マナウス・フリーゾーン」(山岸照明氏(アマゾナス日系商工会議所 前会頭・アマゾナス州工業連盟理事))との指摘があるように、首都サンパウロから2,700km、リオ・デ・ジャネイロから2,800 km(東京とマニラ間の距離)も離れた場所にあり、税の減免は工業製品の運送コストの見返り、すなわちコスト・カバーと見ることもできるわけです。そう考えた場合、理屈の上では、マナウス以外のフリーゾーンから比較対象候補を選定した場合には、運送コストがどの程度かを把握し、コスト・カバー分との兼ね合いも考慮・検討する必要があります。
さらに、マナウス地区は、ポルトガルの占領下に置かれていた時期に要塞が築かれ、治安の悪い地域であったがゆえ、経済特区といえども警備に費用を要してもいます。そのため、比較的治安のよい地域と比べた場合にマナウス地区は、そうした関連コストの負担は重く、本来、それらの差異調整をはかる必要もあると考えられたようです。
いまでこそインターネットの普及により、海外の情報を現地語(ポルトガル語)で入手でき、それらをグーグル翻訳にかけることにより、一定の精度ある情報が入手可能できるものの、上のような様々な差異を、当局が、一定の精度で定量化をはかり行うことには、限界があると考えたとしても不思議はありません。
3 四分位法再考――米国の取扱いと背後にあるCPMの考え方
さて、四分位法をいち早く採用したのは米国でした。米国では、1995年の財務省規則で四分位法の採用を明記し、そのやり方にも触れています。米国内国歳入庁(IRS)は、2000年代に入り、「APA STUDY GUIDE」を公表し、四分位法を採用した場合の具体的な計算なども示しています。
四分位法の採用の背景には、利益比準法(CPM)の採用があると考えられます。
一方、CPMは、経済学的な発想に裏打ちされているともいわれています。つまり、完全競争下の市場においては、市場への企業の参入・退出は自由であることから、仮に市場に何らかの超過利益が生じれば、他企業の参入が生まれ、同じ市場にある企業の利益率が平準化するまで続くと考えられます。逆に市場に何らかの損失が発生していれば、それを回避しようとするだけの企業の退出が生まれ、結局、市場の製品・サービスの提供における需給バランスが保たれるまで続きます。最終的には、市場に残る企業の利益率が、「正常な利益率」で平準化することになると考えられるのです。
そこで、現存する企業の何らかの利益率を用いればよいことになります。その際、統計学的な手法、すなわち四分位法を用いれば、一定程度の異常値を排除できるため精度が上がり都合がよいのです。こうして求められる率が、「正常な利益率」というわけです。
4 改正における懸念と課題
(1)四分位法を移転価格に用いることは万能なのか
統計的手法における四分位法の使用にあっては、(四分位法に限ったことでないのですが)一定の母集団が存在することが統計上前提にあります。移転価格の比較対象取引の候補数のように、せいぜい30程度の場合に、はたして統計的手法が有効に機能するのかが疑問です。ましてや、候補数が1桁というのであれば、その中の1つを排除することにより、求められる数値に大きな変動をきたすこともままあります。例えば、表計算ソフトのエクセルの四分位法を用いた場合、候補数を4階層に区分けして考える四分位法ですが、3社であったとしても数値を算定することが実は可能なのです。
こうした事実に鑑みた場合、たしかに四分位法は統計的には有用な手法であるとしても、そうしたツールを移転価格の比較的少ないデータ数に用いることが本当に統計的な意図にかなったものであるかは疑問となるでしょう。四分位法を万能なツールとして、あまり考えない方がよい、との考えもあるわけです。
(2)CPMに近づかないか
3で見たように四分位法は、CPMの産物ともいえるでしょう。その点を加味した場合、わが国の移転価格税制のうえで、取引単位営業利益法(TNMM)が、CPM化することを名実ともに認めることになるかも知れません。
すでに公開データを利用することを前提に作成されているローカルファイルでは、企業単位の比較対象取引の選定を行い、その結果に四分位法を使用するのが一般的です。その多くはTNMMを移転価格算定方法としています。つまり、わが国のTNMMはCPMと何ら変わらない実務が展開されているといっても過言でなく、かろうじて取引単位のタイトさを拠り所にTNMMといっているだけの感もあるぐらいです。
今回の改正は、そうした実状を、まさに追認する結果になるのかも知れません。
(3)四分位法を採用しない国との相互協議
これまで四分位法は、相互協議において、特定の相手国との間で合意され、採用されるもの、すなわちオプションとの位置づけでした。国によっては、フルレンジを前提としており、四分位法の適用をはなから否定していた国もあります。
しかし、今回の改正により、わが国が四分位法で課税し二重課税が生じた場合には、フルレンジを前提とする国々との間での相互協議においては、二重課税の解消に何らかのコンフリクトが生じる恐れがあるといえるかもしれません。
(4)計算等の詳細な説明が必要
一口に四分位法といっても、先に示したように、エクセルにおいは3つほど方法があり、それらを用いれば簡単に計算ができます。4つの階層に分けることを前提にする四分位法もそれらを用いれば、仮に候補が3つであっても計算上は算定ができるのです。米国IRSは、通達やAPAマニュアルを通じてその計算方法などを示しています。
わが国においても四分位法が正式導入された際には、取扱いの、より詳細な説明が必要となると考えられます。
5 まとめ
今回の移転価格関連の税制改正において、移転価格の専門家にとっては、いわゆる所得相応性基準の導入は予期されたことといえます。しかし、2回にわたり取り上げました差異調整にからむ四分位法の採用は、課税局面での初めての登用だけに、いわばダークホース的な改正との印象を、筆者は強く抱いています。
それは、紙幅の関係で説明を省いていますが、1995年版OECD移転価格ガイドラインの作成にあたり、当時、米国が移転価格ガイドラインに反映しようとしていたCPMを、他のOECD加盟国とともに反対し、TNMMとした歴史的経緯を知る者としては、隔絶な感を抱きもするからです。また、今回の改正が通れば、34年の時を経て、わが国が、米国の当時直面していた諸事情を真に理解するに至った証ともいえるのかも知れません。
さて、はたして今回取り上げた改正が納税者にとって、課税リスクが高まる方向に向かうのか、それとも、当局と同じ発想で差異調整を行うことができ、実務上、使い勝手のよいものになるのか――。
今後の改正内容を注視しておく必要があるように思われます。
(このテーマ終わり)