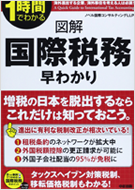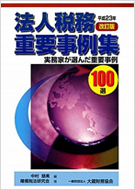平成31年度税制改正大綱公表―移転価格税制の見直しについて(その3) ~移転価格算定方法の1つにDCF法

今回は、無形資産の独立企業間価格の算定方法として、いわゆるDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)を移転価格算定方法の一つとして用いることができる、ことについて取り上げます。
1 これまでの税法等におけるDCF法の扱い
DCF法とお聞きになられ、初めての方もおいででしょう。ただ、DCF法は、決して目新しいものではありません。筆者の手元に、わが国の管理会計のフロンティといってもよい岡本清・一橋大学名誉教授が著された『原価計算』(三訂版)があります。本書は1980年1月に発売となっていますが、すでにそこで「内部利益率法と正味現在価値法の総称としてDCF法(discounted cash flow method)」がある旨が説明されています。筆者も本書で意思決定会計を学んだ一人であることから、すでに40年近く前から知られている方法なのです。
また、例えば、退職給付会計では「割引率」が用いられますが、これはまさにDCF法の「割引現在価値」と同じ発想であり、すでに会計処理においてもDCF法のフレームワークが入り込んでいるわけです。
では、税法の世界では、これまでどうであったのか?――となると、実は法人税法でも、DCF法は明示的に認められているのです。具体的には、平成10年12月4日の「適正評価手続に基づいて算定される債権及び不良債権担保不動産の価額の税務上の取扱いについて(法令解釈通達)」(課法2-14、査調4-20)のなかで、「適正な収支予測額及び割引率等に基づいて算定されたものである場合には、貴見のとおり取り扱うこととします。」としました。ここでの「貴見」には、付録として「流動化目的の債権の適正評価方法のフローチャート」のほか、「債権CF割引法」「割引率の設定について」の表題の他の付録に詳細事項があり、まさにCDF法であったわけです。
2 DCF法とは
将来生み出すと予想されるキャッシュフローを、一定の割引率を適用して割り引いた割引現在価値の合計金額をもって評価額として算出する方法です。
DCF法の構成要素は、①予測便益、②割引率、③期間ということになります。この情報をもとに、予測される将来のキャッシュフローを算定します。そして、一定額の譲渡対価や、無形資産を貸与する場合は貸与期間で除した金額を各期のロイヤリティ収入とするようにロイヤリティの計算を行うことになります。
3 DCF法とこれまでの移転価格算定方法との相違点
DCF法と従来の移転価格算定方法との相違点は、「時間軸」で見た場合に、これまでの移転価格算定方法が、過去あるいは現時点を扱っていたことに対して、DCF法は、将来を扱っている点です。つまり、「予測値」が加味されている点が大きくことなっています。そのことは、予測の合理性に基づく適正性が大きく「評価」に影響を与えることを意味してい
ます。
では、従来の移転価格算定方法にも「評価」という側面はなかったのか、という疑問が湧いてくることでしょう。
比較法の世界である基本三法やTNMMにおいては、あくまでも非関連者取引との「比較」により独立企業間価格を求めていることから、そこに評価は出現しません。
日本と海外の法人の両方で重要な無形資産を有している場合に、残余利益分割法が用いられることが通常であることから、あたかも残余利益分割法は、無形資産の「評価」を行っているかの如く見えますが、実際は違います。
関連者間取引にかかわる日本および海外の関連者のそれぞれの利益(通常、営業利益)を合算し、そこから、比較法に基づく基本的利益を各々の関連者が控除し、残った合算の営業利益を、(寄与度利益分割法のように)利益の寄与する分割ファクターに基づき分割しているに過ぎません。残余利益分割法においても、「評価」の作業は一切行われていないのです。
寄与度利益分割法と残余利益分割法の残余利益を分割する段階だけに着目すれば、第三者との比較による比較法の世界すら顔を出さず、あくまでも関連者間内にある何らかの分割ファクターにより「分割」を試みるわけですから、「評価」という積極的な行為よりほど遠い、きわめて内向き行為を行っているに過ぎないのです。
つまり、これまで関連者間同士に重要な無形資産がある場合は、残余利益分割法が最も一般的に用いられてきたわけですが、そこには「評価」という行為はすっかり欠落していたことになります。そこに移転価格算定方法の限界があったといえます。
しかしそのことは同時に、重要な無形資産が価値ある無比のものであるにもかかわらず、それを評価しようとすること自体に限界があったといえるのでしょう。
4 無形資産の評価
無形資産の評価については、多くの書籍が発刊されており、どの書籍においても3つのアプローチ、すなわち、①コストアプローチ、②マーケットアプローチ、③インカムアプローチ、が紹介されています。そして、①については、過去の費用であることを評価できない理由に、また、②については、評価対象物が「価値ある無比のもの」であり、同じものを発見できないことを理由に、各々が採用できないとされています。
上の3で見た「時間軸」をあてはめ検討する時点から見れば、①は過去、②は検討の時点、③は将来となります。DCF法は、③のインカムアプローチの一形態ですから、繰り返しになりますが、時間軸は将来となるわけです。
つまり、DCF法を採用することは、時間軸で将来を対象としており、そこに予測値が加味されるという構造になります。
5 DCFの適用要件の厳格化
これまで移転価格税制の射程距離は、あくまでも過去の実績値でした。23年度税制改正の推定規定の明確化がはかられ、実質的に移転価格文書が導入されました。28年度税制改正によりローカルファイルの作成が義務化されたわけですが、いずれも過去の実績を対象とした移転価格の検証であったわけです。
移転価格における納税者の予測可能性から事前確認(APA)がありますが、そこで用いられる比較対象取引の財務データも過去の実績値であり、その数値から導かれる適正利益率等を将来に援用しているに過ぎなかったのです。
将来の数値の利用は、費用分担契約など極限られた個別問題に対する際に適用されています。これらはAPAのうち、両国の権限ある当局による相互協議というフィルターを通じて例外的に認められるものであったのです。
それだけに今回の税制改正において、無形資産にかかわる移転価格算定方法として「将来」にかかわる移転価格算定方法が追加される限りは、そのフレームワークともいえる適用にあたっての条件の明確化がはかられねばなりません。
そこでもう一度、税制改正大綱を見てみましょう。
「独立企業間価格の算定方法として、OECD移転価格ガイドラインにおいてまる比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法として有用性が認められているディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)を加える。
これに伴い、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場合の推定課税における価格算定方法に、国税当局の当該職員が国外関連取引の時に知り得る状態にあった情報を基にしてDCF法により算定した金額を独立企業間価格とする方法を加える。」とあります。
ポイントは3つです。
①比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法であること
②独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場合の推定課税において用いられること
③国外関連取引の時に知り得る状態にあった情報を基にしてDCF法により算定すること
まず、①については、4からわかるように、コストアプローチ、マーケットアプローチが使用できず、換言すれば、既存の移転価格算定方法が利用できない場合と限定的であることを示します。
次に、②については、移転価格文書化をはかっていない、あるいは、必要性を当局から説明を受けても応じない、いわば調査に非協力的な納税者に限定されることを意味するでしょう。
最後に、③ですが、これは当局担当者の「後知恵」を禁じるものです。後知恵は、調査時点に判明している状況や環境下で調査官が物事の判断を行わないということです。あくまでも、「国外関連取引の時」の状況下の判断要素や情報にもとづくということです。
実際の運用にあたっては、おそらく③が問題となることでしょう。なぜなら、②から調査に非協力的な納税者から、取引時点で知り得た情報を入手し、取引の時の金額の推定をしなければならないからです。そこでの立証責任は、当局側にあるといえるでしょうから、その作業は慎重に行わねばならないのでしょう。
調査法人が、そもそも取引時点で知り得た情報とは何だったのかを特定しなければなりません。それができたうえで、調査法人が、取引時点で知り得た情報を調査法人および国外関連者の内部情報からどれほど入手可能か。そのような資料が、はたしてあり得るのか、また、第三者から客観的な情報が得られるのか。仮に、得られたとしてもそれらを数値化でき対価の額にまで落とし込むことが可能かなどが、おそらく問題となることでしょう。
DCF法の実効性は、まさにここにかかってくるものと思料されます。
6 まとめ――ファイナンス理論の導入
無形資産の評価においてDCF法を採用するということは、実は、ファイナンス理論を用いることが認められることに他なりません。ファイナンス理論とは、キャッシュフローで物事を考えていくことといえます。
これまでの移転価格算定方法は、取得原価主義による過去の金額にもとづくものであり、財務諸表3表のうえでは、損益計算書と貸借対照表をベースに構築されている方法でした。そこに、キャッシュフロー計算書にもとづく方法を導入しようというものだと、今回の改正を理解することもできるわけです。
では、今日、盛んに取り扱われるファイナンス理論が何を標榜しているかとなれば、それは企業価値の評価です。企業価値とは、将来獲得するキャッシュフローの大きさのことであり、それがいくらになるのかを評価するのがファイナンス理論に他なりません。このことは、M&Aでファイナンス理論がワンセットとなり議論されていることからもわかるでしょう。
こうした見方をした場合、移転価格の世界に、ファイナンス理論が取り込まれ、キャッシュフローに注視した考え方が今後、徐々に入ってくる可能性、あるいはその潮流がはじまったことを意味するのかも知れません。
その意味においても、今回のDCF法導入は、わが国の移転価格税制のみならずグローバルな移転価格のフレームワークにおけるターニングポイントといえ、今後の動向により注視していく必要があるものといえるでしょう。
(本シリーズ終わり)