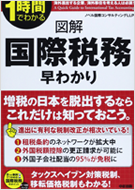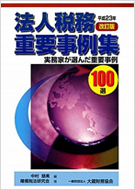近年の税制改正から見る、わが国の移転価格税制の残された重要な改正点

1 はじめに
タイトルが、少々(いや、かなりでしょうか?)大袈裟なようですが、今回は、実質的に令和最初の税制改正となりました平成31(2019)年度税制改正や昨今の税制改正を通じて、わが国の移転価格税制について考えてみたいと思います。
2 移転価格にかかわる税制改正の潮流
平成31(2019)年度税制改正については、すでに本ニュース欄で4回にわたり取り上げたところですが、それらの改正が、まさに税制改正大綱が記すように「(OECDの)「BEPSプロジェクト」の勧告により改訂されたOECD移転価格ガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます。)等を踏まえ、次の見直しを行う」(かっこ書きは筆者)のであって、もはやわが国の移転価格税制は、ガイドラインと一枚岩になりつつあります。
その傾向は2010年版ガイドラインで顕著にあらわれ、移転価格算定方法の優先順位の見直し、ベリー比の明記、独立企業間レンジの採用、シークレットコンパラの否定的な見解などが併記されました。続いて平成23(2011)年10月の税制改正では、いわゆる「最適手法」の新設、レンジやシークレットコンパラブルの運用の明確化がはかられ、平成25(2012)年の税制改正では、ベリー比が新設されています。
3 「どうして今なのか」から発せられる疑問
2019年3月12日付の本コラムにおいて、四分位法の採用について、「いわばダークホース的な改正との印象を、筆者は強く抱いています」と書きました。
たしかに、ガイドラインのパラグラフ3.57では、「また、比較可能性の程度が劣るポイントを除外するためにあらゆる努力を行ったとしても、それによって得られるものは、比較対象の選定に使用されたプロセス及び比較対象につき利用可能な情報の制約の下で、特定又は定量化できずそれゆえ調整することもできない一定の比較可能性の欠陥が残っていると考えられる数値の幅という場合もあるかもしれない。そのような場合、数値の幅の内にかなりの数値が含まれているであれば、統計的手法を用いて、中心傾向に沿って幅を狭めると(例えば、四分位幅やその他の百分位値)、分析の信頼性に向上に役立つかもしれない。」(下線は、筆者による)といっていることから、これに則したかたちで今回の改正が行われるというのも1つの理屈でしょう。しかし、それではなぜ、今なのか?――という思いが残ります。
上の3.57は、2010年版ガイドラインで新設されたものです。約9年の年月を隔てて採用されることになります。こう書くと、いや、ガイドラインにあり改正に資するのであれば、タイミングはいつでもよいのではないか、というご意見も当然あることでしょう。筆者も実を取り、より良くなる改正であればよいと考えています。その一方で、もっと大きな改正すべき点が他にもあるではないか、という思いが募るのです。
4 なにゆえ「資産に対するウェイト付け」は後まわしなのか
ズバリそれは、移転価格算定方法のTNMMの中で「営業利益が資産に対してウェイト付けされている場合」です。具体的には、総資産利益率 (ROA)や使用資本利益率(ROCE)などの貸借対照表項目を用いた利益指標です。
最新となる2017年版ガイドラインにおいてこの項目は、「第二章:移転価格算定手法」(「手法」も「方法」も同義です)の「第Ⅲ部:取引単位利益法」の中で、「営業利益が売上に対してウェイト付けされる場合」「営業利益/原価の場合」に続き「営業利益が資産に対してウェイト付けされている場合」としてパラグラフ(以下、「パラ」といいます。)2.103とパラ2.104が書かれています。
なんだ、2017年版からか、と思われる方もおいでかも知れませんが、そうではありません。驚くことなかれ、この2つのパラは、1995年版ガイドラインのパラ3.26と3.27にルーツを置き(2010年版以前は、第2章及び第3章で移転価格算定方法を記載していました。)、その「第3章:その他の方法」の中で書かれていたのです。それが2010年版で「第2章:移転価格算定方法」にまとめられ、概ね現在のかたちになっているのです(2010年版ではパラ2.97とパラ2.98)。
つまり、1995年当時から、「資産収益率」としてあったわけです。であるにもかかわらず、どうしてこれが税制改正により、わが国の移転価格税制の中に取り込まれないのかが疑問です。なぜなら、わが国の実務において「資産収益率」が利用されているからです。
5 実務での利用
日本の移転価格税制に資産収益率に関する規定がない以上は、当然、調査の局面では利用されません。実務のうえで利用されているのは、事前確認(APA)においてです。
米国では、資産収益率を移転価格算定方法として法令上認めていますから、日米の相互協議をもとにしたバイラテラルAPAでは、合意されているケースがあるのです。しかし、わが国の法令では認められていないわけですから、相互協議の合意が国内法をオーバーライドしたかたちになっています。このことは、租税法律主義の観点からは、奇妙なこととなります。
6 ドキュメンテーションとの関係
こんなケースを想像してみてください。米国親会社、日本子会社であり、米国親会社が日本子会社との国外関連取引において検証を行う際に、何らかの資産収益率(例えば、総資産営業利益率)を用いたとしましょう。これにより、移転価格文書たるローカルファイルが作成されていたとします。
そこで、日本子会社が、その親会社が作成したローカルファイルを、自らのローカルファイルとして日本の税務当局に提出または提示できるか、という問題があります。
これに対しては、結論からいえば「できない」となります。移転価格事務運営指針では、2-4(2)により、これを利用できるように読めますが、当局の見解では、これはあくまでも国外関連者(この例では米国親会社)が、わが国の移転価格税制に則ったローカルファイルを作成している場合であるとの見解を示していることから、上の結論になるわけです。
7 DCF法を採用した意義
わが国の移転価格算定方法は、これまで損益計算書内の項目で完結していました。しかし、平成31年度税制改正によりディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)が採用されることで、財務三表で見た場合に、貸借対照表を飛び越え、キャッシュフロー計算書にまで足が伸びたことを意味します。
DCF法が扱う利益は、予測値が加わったものです。損益計算書と貸借対照表がともに実額、つまり取得原価主義や実現主義を根底に置いていることとは異なるのです。その意味において、現行の基本三法や利益法とは発想が根本的に異なります。
ファイナンス理論に基づきDCF法を採用し、いきおいキャッシュフロー計算書に飛ぶ前にやるべきことがあったのではないかと感じます。
8 おわりに
資産収益率の適用においては、いくつかの問題があります。筆者の個人的な考えでは、法令化された場合に適用できる取引は、例えば、金融取引と長期多額投資を必要とする企業の取引などであり、他の移転価格算定方法よりも限られたものとなるでしょう。しかし、実際に適用できる可能性のあるケースがあれば、そしてまた、現実にAPAで採用されている以上は、ガイドラインにも記載があることですから、少なくとも道具立てとして準備されて然るべきものではないのかと考えます。早急の税制改正による法令化が待たれる1つです。
以 上