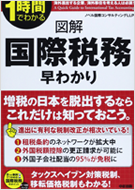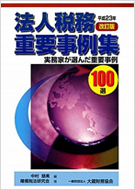調査の現場から(1)~適正利益率レンジから外れている?

本シリーズについて
本シリーズでは、実際に調査において調査官が納税者(会社)に対して指摘した事項について、読者に参考になることを採り上げ、不定期に連載するものです。内容については、汎用性を持たせる意図から、簡略化や一部修正を加え説明を行いますので、ご了承ください。
事案の概要
- 日本で製造業を営む親会社Pは、グループ全体のコスト低減をはかるため、製造移管を行い、アジア諸国を中心に製造子会社を有している。
- その内の1つの子会社Sの直近3期の売上高営業利益率の平均は15%である。
- Pは、Sとの国外関連取引は、ローカルファイルの作成基準未満の金額であったが、Pは自発的にローカルファイルを作成していた。
- ローカルファイルでは、Sを検証対象としていた。
- ローカルファイルでの適正利益率レンジは、TNMM(取引単位営業利益法)により、売上高営業利益率を利益水準指標とし、比較対象取引(企業)12社に基づくフルレンジ(7%~16%)を採用していた。
- なお、PとSとの国外関連取引は、製造部品にかかわる棚卸資産取引のみであった。
調査担当者の指摘事項
- 売上高営業利益率15%は高く、所得移転の蓋然性がある。
- 所得の蓋然性の検討に当たっては、一般に四分位(インター・クォータイル)レンジが用いられており、仮に四分位法を用いれば、適正利益率レンジの上限値は10%となる。
- 2.のことから、上限値(10%)と実績値(15%)との差額5%部分がSへ所得移転している。
- Pは、製造移管を行う目的からSを設立しており、差額5%部分は、PからSへの技術供与に基づくものであり、Pは、Sから技術使用料(ロイヤリティ)として5%部分を回収すべきものと考える。
納税者の反論
- 調査担当者の指摘事項のうち1.については、該当しないものと考える。
- 同指摘事項の2.については、フルレンジを用いているのは、選定した比較対象企業は、きわめて比較可能性の高い取引(企業)、つまりベスト・コンパラ(比較対象取引(企業))と判断しており、フルレンジの使用は認められるものと考える。
- Sは、当該国に進出して年数が経っており、Pから特別な技術供与はない。また、Sは製造ノウハウを形成しており、日々、独自に製造方法の見直しや改善を行っている。
- Sの現地の営業担当者が、マーケット戦略により、積極的に進出国の顧客営業を行っており、それらが功を奏している。
- 3.および4.の理由から、比較的に高い売上高営業利益率を維持しているものと考えている。
- 以上の理由から、所得移転の蓋然性はなく、調査官の指摘事項は失当と考える。
チェックポイント
チェックポイントの第1は、「所得移転の蓋然性のチェック」です。
初めてお聞きになる方もおいでかも知れませんが、移転価格の調査の初期段階で、「本当に移転価格の問題があるのか・ないのか?」を見極めることを指します。いわば、業界用語です。
移転価格の調査は、これまで概して2-3年を要してきました。税務当局としても、限られたリソースと調査日数の中で、より効率的に調査を行う必要があることから、調査の初期段階で「蓋然性」をチェックするのです。
チェックポイントの第2は、「四分位法」です。
「所得移転の蓋然性のチェック」の段階では、詳細な事業把握はいまだ行われておらず、それゆえに、比較対象取引(企業)の候補を高い精度を持って行うことができないことから、慣行的に、四分位法を用いることが多くあります。
四分位法は、統計手法の1つです。比較対象取引の率に着目して、候補を4つのグルーに分け、上下25%の集団を除外し、残りの50%を信頼が置けるものとして、その集まりが示す値を用いるというものです。言い換えれば、不純物が混ざっているかもしれないから、極端に高い値と低い値を除外するのです。つまり、四分位法は、あらかじめ不純物があることを前提としていると言えます。
しかし、「納税者の反論」の2.のとおり、比較対象取引がベストのコンパラであれば、あえて四分位法を使用する必要はないのです。
チェックポイントの第3は、「蓋然性は感覚で判断してはダメ」です。
調査担当者が、Sの売上高営業利益率を高いと感じるのは、それは、単なる感覚や直感に過ぎません。適正か・高いかの判断は、あくまでも比較対象取引(企業)を選定して、第三者の数値で行わなければなりません。
チェックポイントの第4は、「取引単位を混同してはならい」です。
本件の国外関連取引は、「事案の前提」の6.にあるように、「PとSとの国外関連取引は、製造部品にかかわる棚卸資産取引のみ」です。ですから仮に、調査担当者が指摘する5%部分が高いとしても、それは、棚卸資産取引に関わる問題と、一義的になるはずです。
ここで、次の通達を確認しておきましょう。
移転価格事務運営要領(指針)
(無形資産の使用許諾取引)
3-14 法人又は国外関連者のいずれか一方が保有する無形資産を他方が使用している場合で、当事者間でその使用に関する取決めがないときは、譲渡があったと認められる場合を除き、当該無形資産の使用許諾取引があるものとして当該取引に係る独立企業間価格の算定を行うことに留意する。
なお、その使用許諾取引の開始時期については、非関連者間取引における例を考慮するなどにより、当該無形資産の提供を受けた日、使用を開始した日又はその使用により収益を計上することとなった日のいずれかより、適切に判断する。
(注)下線は、筆者による
調査担当者の念頭に、通達3-14があるのかも知れません。つまり、表面上は棚卸資産取引であるものの、その取引の中には、実質的に、無形資産の使用許諾の取引も含まれているとの判断が働いているのかも知れません。
しかし、その場合には、下線のなお書きの各事項を検討しなければなりません。
そもそも、TNMMは、一般に、検証対象に無形資産のないケースに用いられる移転価格算定方法(TPM)です。TNMMの採用に当たっては、その前段階で、機能リスク分析により、TPMを決定しているはずです。
仮に、調査担当者が、上のことを主張するのであれば、自らの機能リスク分析の結果を納税者に示し、S社には、こうした無形資産がPから許諾されていると示さねばならないでしょう。それを行わずして、「PからSへの技術供与に基づくものであり、差額5%部分は、PがSから技術使用料(ロイヤリティ)」とみなし、その部分が、Sに移転していると主張することは、拙速の感を否めないでしょう。