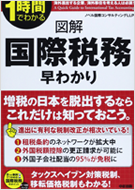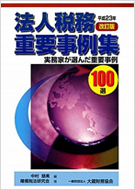米国大統領選、トランプ氏勝利が国際課税に及ぼす影響

トランプ氏が大統領で再選されました。今後、国際課税の分野で、どのようなことが起き得るかを、2点取り上げ、考えてみたいと思います。
第1の柱~デジタル課税
国際課税の大きな取組みとして、ご存じのGoogle、Amazonといったグローバル規模で事業を展開するプラットフォーマに対して、世界的に課税をしようという動き(「デジタル課税」と呼ばれています)が、頓挫してしまうことが危惧されます。
デジタル課税の問題については、2012年から経済協力開発機構(OECD)で開始されたBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトで議論がスタートし、ようやく2021年10月、世界136カ国・地域の間で合意に至りました。あとは米国議会の条約批准を待つばかりとなっていましたが、米国通商代表部(USTR)と米国財務省は、実質的に、大統領選を理由として合意の延期をはかっていたのでした。
このような状況下、トランプ氏(共和党)が勝利を収めのです。
そもそも、デジタル課税の狙いは、グローバルに事業活動を展開するものの、これまでの課税ルール(恒久的施設(PE)なければ、事業所得課税なし)では課税できない企業に対して課税するものです。GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)なるプラットフォーマは、まさに米国企業であり、それらを加えたデジタル課税の対象(売上高200億ユーロ(約3.3兆円)超)となる企業の多くは、米国企業と考えられています。
そうであれば、米国第一主義をとなえるトランプ氏が、米国の税収がみすみす減ってしまこの税制を認めるとは考えづらいでしょう。また、SNSを駆使して事業活動を展開しているイーロン・マスク氏が選挙戦を支援していたことから、マスク氏の反対などを受け、デジタル課税の条約批准を拒絶することも考えられるでしょう。
つまり、デジタル課税の合意の見込みは、事実上なくなったと言えるのではないでしょうか。10年以上に及んで行われた議論は、ここに水泡に帰すわけです(あるいは4年間棚上げに)。
事態は、これだけに終わらないでしょう。
デジタル課税の議論がない時期には、インドやフランスなどの諸国は、独自に、デジタル・サービス税(DST)を導入し、プラットフォーマに対して課税を行ってもいたのです。これに対して、先のトランプ政権下では、フランスであれば、ワインなどに報復関税を課し対抗する措置をとり、通商関係が険悪な状況に陥ったのです。このような状況を善しとしないOECDが、デジタル課税をグローバルで採択し、DSTを導入・施行している国々に矛を収めさせたのです。
今後、デジタル課税の合意が頓挫してしまうことにより、一度棚上げしたDSTを用いてプラットフォーマに対して課税し、米国は米国で、関税の際限ない報復を行うといった、自由経済にもとづく国際貿易に歪みが生じ、最終的に、消費者たる国民が不利益を被る事態が想定されます。
グローバル・ミニマム課税
いま1つが、グローバル・ミニマム課税です。これは、年間総収入金額が7.5億ユーロ以上の企業が対象で、日本では、800社~900社が見込まれています。
これについては、日本では、昨年の税制改正ですでに制度化され、3月決算の企業であれば、まさに、いま走っているこの事業年度が最初の適用事業年度となります。
この制度は、日本の企業が親会社であれば、その海外子会社などの実効税率が15%を下回っている場合、15%までの不足分を日本の税務当局に納税するというものです。これは、いわゆるタックスヘイブンなどの低税率国に会社等を設立して税逃れをはかる行為を阻止しようという取組みです。
ところが、トランプ氏は、米国の法人税率を15%にすると選挙戦の公約で言っていました(2024年9月6日付Bloomberg電子版)。もし15%になれば、米国の子会社等がその他の税恩典(例えば、日本の租税特別措置法に規定される事項)などを受けていた場合、実効税率が15%を下回る可能性が出てきます。
そのため、日本の企業等で米国に子会社等を有している場合は、より厳密に、実効税率の算定を行う必要が生じてきます。
まとめ
トランプ大統領の新体制下では、国際課税の分野においても大激震が走りそうです。今後の動向に注視する必要があるでしょう。