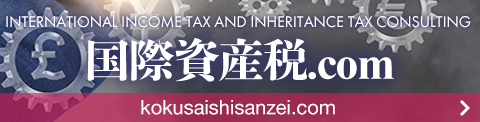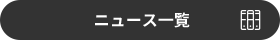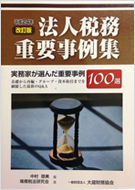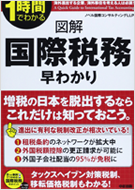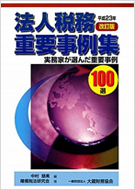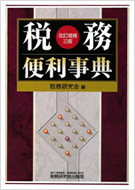SBI系、移転価格課税34億円から学ぶ、御社の処理

報道によれば、東京国税局は、SBIホールディングスの子会社に対して、中国の関連会社からサービスを受けた際の対価支払いが、通常支払う金額に比較して多額であるとして、移転価格課税を行った模様です。
課税の根拠は、対価支払の内訳となる人件費が、通常の3倍以上だったことが要因のようです。つまり、移転価格税制による所得移転金額の算定では、移転価格算定方法の1つである、「独立価格比準法」が適用されたと考えられます。
課税金額が34億円とインパクトのある金額だったからか、新聞だけでなく、NHKの正午のニュースでも取り上げられ、全国規模の報道にもなりました。
さて、この報道を、対岸の火事とせず、もしみなさんの会社が海外子会社などを擁しているのであれば、この機会に会社の処理をチェックされてはいかがでしょうか。
想像される事実関係
今回の課税は、中国の関連会社から、グループ内のシステムの開発や運用に関するサービスの提供を受けていたことから、おそらく、委託契約などを結んでいたことでしょう。そうした契約は、通常、「請負契約」または「準委任契約」に分類される契約ではないか、と考えられます。
税務調査アプローチ
当局が行う移転価格の調査では、契約内容がチェックされます。OECD移転価格ガイドラインにおいても、契約内容を確認するよう書かれています。
成果物の完成を目的とする請負契約であろうが、何らかの業務の遂行を約する準委託契約であろうが、通常、契約をする際は、「見積書」があるでしょう。支払う対価の「内訳」あるいは「積算」があらかじめ行われることでしょう。本件のような場合は、「人工(にんく)」や「作業員」などが、どの程度の工数(こうすう)を要するのかを、日数や時間で示され計算されることでしょう。
つまり、「金額=@単価×日数(時間)」により、支払額が決定されることになるわけです。この@が、今回のケースでは、3倍もあったということでしょう。
では、この3倍――どうして3倍だと分かったのでしょうか。
移転価格の比較対象取引となる「第三者の取引」を見つけ出すのは、困難が伴います。
内部比較対象取引
1つのアプローチとして、いわゆる「内部比較対象取引」なるものがあります。これは、会社が、親会社や子会社などの関連会社とのみ取引を行っていなければ、第三者との間で過去・現在において、同一または類似の行為を依頼している場合、それが比較対象取引になる場合があるということです。これを、内部比較対象取引と呼びますが、現に第三者との取引だけに、比較可能性が高いという特徴を有していると、一般に、理解されています。
まずは、みなさんの会社において、関連者取引と同一または類似の取引があれば、上のような着眼点を持ち、分析・検討をしてみるのがよいでしょう。
給与から分析してみる
業務に従事する人員の工賃、つまり単価が適正であるかが、内訳から明確に判別できない場合があるかも知れません。しかし、納期作業や契約期間から、人工の単価を推計することはある程度可能でしょう。
例えば、JETRO(日本貿易振興機構)では、次のサイトにおいて、「ビジネス情報検索」ツールにより、「投資コスト比較」データを公表しています。
https://www.jetro.go.jp/world/search/cost.html
これにより、各国・地域別における賃金を、製造業・非製造業などで区分し、課長クラスやスタッフなど、職位ごとの月額を把握できます。また、賞与や社会保険料などを知ることもできます。
仮に、年間の稼働日数を220日~230日程度とすれば、年額の稼働日数で割れば、日数当たりの単価が算定できるでしょう。その金額には、請求する会社の利益部分は含まれていないでしょうが、比較結果に大きな差異が認められる場合、税務調査に備え、あらかじめ詳細な説明資料や明細を準備しておく必要があるでしょう。
契約ごとの利益(率)を検討しておく
国外関連者は独立した企業体とされていますが、税務調査においては、身内と見なされることがあります。それゆえに、所得移転があるのではないか、と疑われるわけですから、特定の契約に係る利益や利益率を、国外関連者から入手しておくことも有用でしょう。
依頼している作業について、総コストを示し得るよう、何らかの資料を得ておくわけです。国外関連者のバックオフィスで発生する間接費まで正確に集計することは難しいものの、粗利ベースで大まかな数値を把握し、極めて多額の利益や利益率になっていないかを確認しておくことも有用でしょう。そして、可能であれば、委託契約の内容と同一・類似の業務を事業としている会社を、データベースから抽出して、利益率等のデータを収集・分析しておくことも、税務調査に備えた効果的な対応策の一つと言えるでしょう。
「一式」はあり得ない
会社にあっては、国外関連者との取引については、大枠で原契約を締結し、以後は、それに従い、金額は、「原契約に従う」「一式」という契約が締結されている場合も考えられるでしょう。そして、当該原契約については、何年も、あるいは十数年にわたり、見直しや変更が行われていない可能性があります。
この事実こそが、関係会社間の「なーなーの取引」として、移転価格で詳細に検討されるきっかけとなり得るのです。
以上の視点などから、御社と国外関連者との契約や関連書類を、この機会に一度見直されてはいかがでしょう。