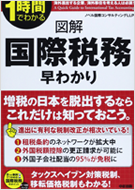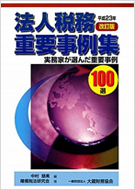移転価格と知的財産法との関係(その2)

重要な無形資産と残余利益分割法
日本の法人と海外の法人ともに重要な無形資産がある場合、移転価格算定方法としては、従来、残余利益分割法(RPSM)が用いられてきました。令和元年の税制改正において、DCF法がその1つに加わりました。
しかし、DCF法は、無形資産が、「特定無形資産」に該当し、当該無形資産の譲渡を行うなど、いわば例外的な局面で用いられる手法といえるでしょう。ですから依然として、RPSMが主流といえるでしょう。
皆さんの中には、RPSMを用いることにより、無形資産の「評価」をしていると思われている方がおいでかも知れません。しかし、それは、誤解です。
RPSMは、日本の会社と海外の会社の①合算利益(通常、営業利益の合計金額)から、互いに果たす機能のうち、該当する事業を行なえば、通常、得られるであろう②利益部分(これを、「基本的利益」あるいは「基礎的利益」と呼びます。)を求め、①から②を控除した残りの部分を、無形資産の形成・維持・発展に寄与した要因(ファクター)により、③分割しているに過ぎません。
ですから、表現を変えれば、②の利益分を上回る利益があれば、その部分を、「重要な無形資産」から生じている利益として、「間接的に」認識しているに過ぎないわけです。
つまり、そこでは、重要な無形資産は、依然として曖昧なかたちのまま「金額」があるに過ぎないのです。
知財訴訟を意識した対応を
これまで移転価格の実務では、上のようなアプローチにより、通常の利益を超える部分があれば、それを「重要な無形資産」として認識されてきた帰来が、多分にあります。
しかし、令和元年の税制改正により、「特定無形資産取引」なる概念と、それに関連する「価格調整措置」が導入されたことにより、より厳密に、重要な無形資産を認識する必要が生じてくるような案件も生じてくるように思われます。
そのように考えると、知的財産法の存在が、グッと身近に感じられるのではないのでしょうか。
前回(「移転価格と知的財産法との関係(その1)」)で見たように、特許権、実用新案権からはじまり諸々の知財法が、移転価格税制における重要な無形資産の存否や評価などの判断に用いられるように、法令上は、規定されています。
証左の1つとして、税の訴訟において、知的財産高等裁判所(知財高裁)が判断を下した事件(知財高判平成22年5月25日税務訴訟資料260号順号11443)が挙げられます。
当該事件は、ソフトウェア開発に関する国外関連取引にかかるロイヤリティの案件です。当初、地裁で争われ、国側勝訴となったところ、納税者が、控訴先の裁判所を、「知財高裁」としたのです。
知財高裁は、文字通り知財を扱う専門の裁判所です。納税者は、一審で無形資産の検討が十分にされなかったと感じたのでしょう。そこで、「餅は餅屋」と考え、知財高裁で争うことにし、結果的に、納税者が逆転勝訴したのです。
こうした事実を見ると、課税庁は、より厳密に重要な無形資産を検討する必要性を感じていることでしょう。
一方、納税者から見れば、無形資産の形成・維持・発展を行っている、まさに当事者ですから、より詳細かつ厳密な内容や事実関係がわかっているわけです。課税庁と意見を異にする場合、そのような事実関係等をもとに、より強力な反論を試みることもできるでしょう。それを、知財の専門家たる裁判官に聞いてもらい、判断(判決)を下してもらう、という選択肢もあるわけです。
以上の諸点を考えた場合、移転価格税制を、単に租税法の1つの法令と捉えるのではなく、多角的な視点で捉え直すことも、事案によっては、必要なことになってきたと思われますが、いかがでしょうか。
(参考)本稿と同様の視点で論じられた良書として、『租税と法の接点~租税実務におけるルール・オブ・ロー』(佐藤修二弁護士・大蔵財務協会)がございます。知財高裁に関しては、153頁-156頁が参考になることでしょう。
(注)本稿の作成に当たっては、弊法人代表社員の井藤正俊著『移転価格の実務Q&A』(清文社・2020年)「Ⅶ 無形資産」(299頁~396頁)を参考にしています。