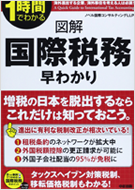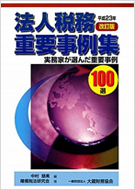OECD移転価格ガイドライン(2022年版)特集(1)残余利益分割法の分割ファクターに、累積費用の使用の余地も

重要な無形資産は1日では成らず
企業に超過収益をもたらす重要な無形資産は、文字通り1日では形成されません。1年、いや数年かけても形成することが難しいのは、実際に、事業を行っていれば痛感することでしょう。そもそも、そうしたプラス・アルファを得られるよう、どの企業も懸命に日々、研究開発を行っているのが実状なわけですから。
いま仮に、日本の親会社と海外の製造子会社とが超過収益をもたらす何らかの重要な無形資産を有しているとしましょう。このようなケースでは、通常、移転価格算定方法(TPM)としては残余利益分割法(RPSM)が用いられるでしょう。
ただ、このRPSMという手法は、実に多くの問題点を含んでいます。実際、税務当局がRPSMを適用して課税し、これを不服として納税者が提訴したケースでは、実に数々の争点であらそわれているのです。
争点の1つに、超過利益である残余利益を分割する分割要因(分割指標、分割ファクターと呼ばれもします)の金額をいくらにするか、があります。
今回扱うのは、その金額を、どのように決定するか――言い換えれば、分割ファクターの金額を1年間の費用で考えるべきなのか、という問題です。
分割ファクターを1年単位で考えることの合理性は?
移転価格税制は、租税特別措置法の「第三章 法人税法の特例」として規定されています。つまり、法人税法の1つの規定なのです。ですから移転価格税制も、あくまでも事業年度の中で独立企業間価格を考えることになります。今や、ほぼすべての企業が、事業年度を1年で行っているでしょうから、仮に、RPSMを適用して独立企業間価格を計算する場合も、この1年の事業年度の「枠」の中で考えることになるわけです。
しかし、どうでしょう。RPSMで扱う重要な無形資産は、1日では形成されないのです。独立企業間価格を計算する、その事業年度内に、ひょっこりとできることなど、皆無といってよいでしょう。
いま、RPSMの分割ファクターとして、研究開発を用いている場合、その事業年度の金額のみを用いればよいのか?――という疑問が、自然とわいてくるでしょう。1年という枠には、窮屈で、どうも収まりきれず、「無理」があるわけです。
2022年版ガイドラインの回答
2.183. 一部の事案において、原価ベースの分割指標の信頼性における重要な問題は、 利益分割指標(例えば、資産、原価その他)を決定するに当たって考慮すべき要素 として適切な期間の決定がある。困難が生ずるのは、費用が発生する時点と価値が 生じる時点との間に時間差が生じる場合があるからであり、いずれの期間の費用を使用すべきかを決定することが困難な場合が時としてある。例えば、原価ベースの指標の場合、単年度ベースの支出を使用することが適切な場合がある一方で、当年度に加えて過年度に生じた累積費用(状況によって適切な場合であれば償却後の純額)を使用する方がより適切な場合もあるだろう。事案の事実と状況によって、この決定は当事者間の利益の配分に重大な影響を与えることがある。上記 C.5.1 節で述べたように、利益分割指標は、事案の具体的な状況に適したものとし、独立した当事者間で合意されたであろう利益分割について信頼できる近似値となるものが選択されるべきである。本節の原則は、本指針第2章別添IIの事例 16に示されている。
(注)下線は、筆者による。
実務上の課題
移転価格のローカルファイルの作成や事前確認(APA)などにおいて、複数度年度による検証を行うことは、これまでの実務でもあります。例えば、売上高営業利益率を、検証事業年度以外に、直近3年、あるいは、5年間の加重平均で計算、検証を行うというものです。
しかし、RPSMは、検証事業年度の計算で求められた結果が、独立企業間価格として、最終的に取り扱われるのが、長年の実務と言えるでしょう。
そのため、仮に、分割ファクターのみを「当年度に加えて過年度に生じた累積費用」を使用するとした場合、まず第1に、それは分割ファクターのみでよいのか、という疑問が生じてくるでしょう。つまり、合算利益についても過年度を考慮しなくてよいのか、という疑問です。
第2に、2.183で述べている「累積費用……を使用する方がより適切な場合」とは、いったいどのような場合なのか、その基準や判断を、どのように行えばよいのかという問題です。
RPSMを適用した後の利益配分が、日本により多く付くのであれば、日本の税務当局は、それこそが「適切」と考えるでしょう。逆に、国外関連者が存する国の税務当局は、不「適切」と考えることも、おおいに想定されます。
実務においてガイドラインが示す方法を用いるには、今後、当局から、何らかの例や指針などが示されることが、期待されます。
OECD移転価格ガイドライン(2022年版)特集(1)残余利益分割法の分割ファクターに、累積費用の使用の余地も