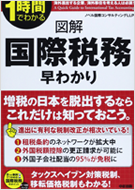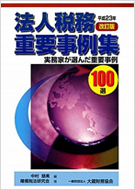「デジタル課税」の行方

米国財務省は、一定水準の売上高と利益率を超える、全世界で100社程度のグローバル企業に対して新たな課税を導入し、各国に配分する案を経済協力開発機構(OECD)に提案しました。
さて、これにより、これまでOECDで議論が行われてきた、デジタル課税の国際ルールづくが進展するのでしょうか。
解説
OECDは、2019年1月、いわゆるデジタル課税に関する「協議文書」を示した後、OECD独自の案を提案するなど、昨年末の合意をめざして議論をしてきました。しかし、コロナ禍となり、また、米国トランプ政権が反対したことから、2021年中ごろの合意・決着をめざしています。
米国がバイデン政権となったことで、今回、新たな提案がされ、OECDでの「決裂」は避けられる見通しが出てきたと、とりあえずは言えるでしょう。
これまでの主要な動きを、ざっとおさらいしてみましょう。OECDは、2012年からBEPSプロジェクトを行い、2015年10月、最終報告書を公表しました。ただ、15あった具体的な行動計画のうち、積み残しとなったものに、電子経済の課税上の課題への対処(行動計画1)、有害税制への対抗(行動計画5)がありました。
そこで、OECDは、第1の柱(Pillar One)と第2の柱(Pillar Two)を示しました。具体的には、第1の柱は、デジタル化された経済の、より広範な課題に対処し、課税権の割り当てをいかに行うかに焦点が当てられた議論です。まさに、GAFAに代表されるデジタル・プラットフォーマーなどに対する課税、いわゆるデジタル課税の議論です。
第2の柱は、BEPSプロジェクトが終了した後も依然として残るBEPS問題で、有害税制への対抗、とりわけタックスヘイブンを利用した租税回避行為を、いかに封じ込めるかの議論です。
今回のバイデン政権下の米国財務省提案は、トランプ政権下でこれまで反対されてきたデジタル課税の議論を前進させるものには違いないでしょう。ただ、米国提案は、いわゆるGAFAに代表されるITやプラットフォーム事業者に限らないものであり、売上高などの金額基準などは示されていません。そのため、とりあえず自国のIT事業者を守る目的からの提案であるとの見方もできるわけです。
昨年までのOECD案では、あくまでも自動化されたデジタルサービスを販売する多国籍企業、または消費者向けビジネスに従事する多国籍企業にのみ適用するとしていました。しかし、米国が、一部「セーブハーバー」基準を設けることを主張したのです。これは、事実上、OECD案を骨抜きにする提案であったことから、議論は頓挫してしまいました。
OECD案は、副次的な効果として、第2の柱の問題の解決の糸口となる側面も認められたことから、混迷を深めたと言えます。
昨年までのOECD案については、計算技術上複雑であり、米国が主張するように「課税権を調整する安定的な仕組みが必要だ」というシンプルな制度が望まれることは、確かでしょう。
しかし、その一方で、デジタル課税の該当となるグローバル企業の数は、世界に冠たる企業であり、その数は一定数に限られ、みずからが人工知能(AI)やコンピュータ技術を駆使し、複雑な計算を行う能力を有しているとも考えられます。
さて、報道では、本年7月に実施される20カ国・地域(G20)財務相・中銀総裁会議までの決着を目指すとされています。米国の提案が、これまで停滞していた議論を加速させるか否かは、デジタル課税に積極的であり、すでに一部の国において課税を行っている欧州各国が、米国案を受け入れるかにより、まだまだ予断を許さないものと考えられもしますが、いかがでしょうか。
関連記事
〜OECDの動き〜
〜わが国の動き〜